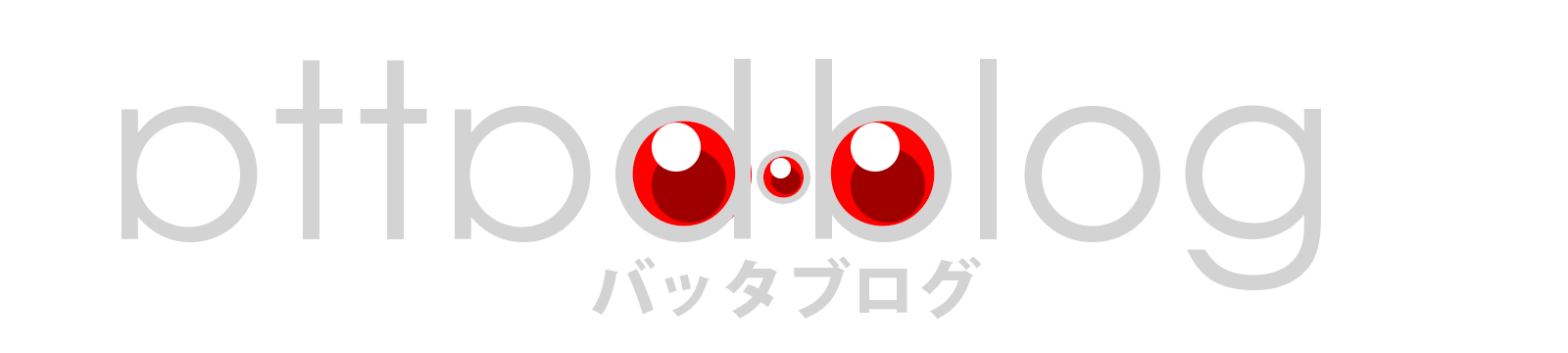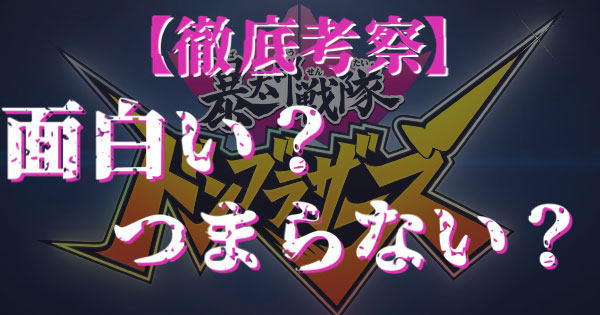88%。
この数字が何を意味するのかといえば、2022年12月現在放送中のスーパー戦隊シリーズ第46作『暴太郎戦隊ドンブラザーズ』を高く評価した人たちの割合である。「ドンブラザーズ」というキーワードでググってみると、概要欄に表示される(2022年10月時点)。
この数字の信憑性は正直なところ、よくわからない。母数も不明だし、どういったリアクションを高評価として判別しているのかが見えない。ただし、これについては見えないからこそ信用できるという部分は間違いなくあるだろう。評価を上げる方法が公になってしまえば、そのために数字を操作する人たちが必ず現れるはずだからだ。
ここで他の作品の評価を考えてみよう。例えば、悪評高い映画『大怪獣のあとしまつ』などは高評価32%となっている。他の作品でググってみても、個人的には割と納得できる数値であり、特定の誰かによる印象操作、のような意図は感じられない。
だから、私は作品の評判を語ろうとする時には、この数字をよく引用する。そして『ドンブラザーズ』という作品については、ネット上で何かしらの意思表示をしたGoogleユーザーが一定数存在して、およそ9割が好意的な評価をしたということには違いない。
ドラマや映画で、およそ9割もの人が高評価をしたとなれば大成功と言っていいだろう。
ところが、同じ特撮ヒーローというカテゴリーの中では、取り立てて高い評価ではなかったりするのも事実だ。
スーパー戦隊シリーズの前作『機界戦隊ゼンカイジャー』でググってみると、これが偶然にも同じ88%となっており、さらにその前の『魔進戦隊キラメイジャー』では91%となる。
当時の各作品に対する世間の評価を覚えている方からすると、なんとなく納得のいく数値ではないだろうか? 少なくとも、『ゼンカイジャー』より『キラメイジャー』の方が世間の評価が高い、という点には頷けるという方は多いはずだ。もちろん、中には「90%? いやいや、100%っしょ!」といった個人の感想もあるに違いない。しかし、あくまでも世間一般としては、という注釈付きなら、それほど違和感のある数値ではないはずだ。
別記事で、歴代仮面ライダーシリーズを順にググってみたこともあったが、その時の最低点でも78%だったから、特撮ヒーロー作品は総じて根強いファンがいる、ということなのかもしれない。
ちなみに『ドンブラザーズ』に対する私の評価はとても高い。少なくともつまらないとは思っていない。しかし、この感覚が世間一般の評価とはズレているかもしれない、ということを感じているのも事実。
というのも、とにかくこの『ドンブラザーズ』はクセが強い。「狂ってる」と言い換えても良いレベルで、普通に特撮ヒーローを期待していたら、間違いなく肩透かしを食らうはずだ。初めから万人受けを放棄しているとしか思えない。制作陣も賛否あることは織込み済みだったろうが、実際に吹き荒れている賛否両論を見ると、心なしか、賛成派の人も、否定派の人も、いつもより鼻息が荒い気がする。
要するに、好きな人はトコトン好きだし、嫌いな人は「シリーズ中、最低」というくらい嫌い、という感じである。
先述したように私は肯定派なので、基本的には大好きである。ただし、否定派の人たちの気持ちがまるでわからない訳でもない。
そこで本記事では、『ドンブラザーズ』否定派の人たちが気になっている部分を洗い出してみることで、『ドンブラザーズ』という作品を見つめなおしてみたいと思う。これは傑作か、それとも単なる駄作なのか? ネタバレも含むが、最後までおつきあいいただければ幸いだ。
全く新しいスーパー戦隊


『機界戦隊ゼンカイジャー』の次作として『暴太郎戦隊ドンブラザーズ』が発表された時には驚いた。
日本の昔話『桃太郎』をモチーフとしたとするスーパー戦隊。それでいて、戦隊名は『暴太郎』。「ボウタロウ?」違う違う。そうじゃない。これで「アバタロウ」と読ませるのであった。なんでも、戦隊名として桃太郎とアバターをどう表現するかで揉めた際、「アバタロウでいいじゃん」と会議参加者の一言で決まったというが、まずこのネーミングからしてよくわからない。
スーツデザインはカッコ悪いとまでは言わないが、決してカッコ良くもない。『桃太郎』をモチーフにしているというだけあって、イヌ、サル、キジがいることは当然だが、何故かオニまでいる。オニは追加戦士だろうと思ったら、まさかのレギュラー。しかも紅一点である(両手の人差し指でツノを表現したポーズはかわいい)。5人の背格好が異様に低かったり高かったりするのも気になるし、桃太郎(レッド)にはちょんまげまでついている。既にこの時点で、純粋なヒーロー作品として胸を高鳴らせていた戦隊ファンたちは、軽い絶望に襲われていたに違いない。
ただし、希望がなかったわけではない。
それは脚本家である。
あの井上敏樹さんがメイン脚本を担当するというのだ。井上敏樹さんといえば、東映特撮とは縁深い方である。2000年以降は、『アギト』や『555』、『キバ』といったコアなファンを獲得している仮面ライダーシリーズのメイン脚本を担当したことで知られているが、1991年2月から1992年2月まで脚本を担当した『超人戦隊ジェットマン』は、もはや伝説級の作品である。当時人気だったトレンディドラマっぽい要素をスーパー戦隊に取り入れるという飛び道具的な試みは大成功。酒もタバコも、さらには大人の恋模様まで描くという、およそヒーローっぽくない作風は、今でも語り種になっている。
あれから30年。井上さんが再びスーパー戦隊の脚本を担当する。しかも、「桃太郎」をモチーフとしたイロモノ設定のスーパー戦隊である。メンバーは10代から30代まで幅広く、その職業も無職や学生からサラリーマンまでとバラエティに富んでいる。
さらに、プロデューサーには白倉伸一郎さんを据えている。東映きっての名プロデューサーであり、井上敏樹さんとは『ジェットマン』の頃からのつきあいである。この二人に共通しているのは、ヒーロー作品だからと言って、勧善懲悪や完全無欠にこだわらないところ。つまりは、人間的な登場人物を描く点だ。この二人が組んでつまらない作品になるだろうか?
加えて、「これまで誰も見たことのないスーパー戦隊を作る」という公式の気合いの入り方も、単なるイロモノを超えた作品を期待させた。
そうしていよいよ放送が開始されてみると、『ドンブラザーズ』は面白かった(個人的には)。そして、確かに今まで見たこともない要素というのも見受けられた。
が、それが新しいか? と問われれば、いささか疑問ではある。「新しい」というよりは、「従来パターン化していた要素をあえて省く」という程度だったからだ。
具体的には、スーパー戦隊ではお約束の全員揃って「◯◯戦隊!◯◯レンジャー!」といった名乗りのシーンがないとか、いつまで経ってもメンバー全員が顔を揃えないとか、戦隊メンバー自らが巨大ロボになるとかいった点が挙げられる。
こういった要素によって、確かに今まで見たこともない作品となっている部分もあるにはあるのだが、それが「誰も見たことのないスーパー戦隊」という言葉に反応していた人たちの期待に応えられているかは微妙なところだ。
とはいえ、純粋に「誰も見たことのないスーパー戦隊」を、ストーリーテリングだけで実現するのは困難を極めるだろう。そもそも物語なんていうものは、シェイクスピアの時代にとっくに出尽くしていると言われているわけで。スーパー戦隊シリーズだって、基本的な構造は変えず、枝葉末節の部分で差別化しているだけである。だから、スーパー戦隊の皮を被ったシチュエーションコメディという作風をもって、「誰も見たことのないスーパー戦隊」とうたうこと自体は、間違いでも何でもない。


遅々として進まない物語


スーパー戦隊シリーズとは、めちゃくちゃざっくり言うと、絶対的な力を持つ悪の大組織とその支配者に、若き少数のレジスタンス(戦隊メンバー)が立ち向かう物語であり、各話は、様々な固有の能力を持つ怪人たちによって巻き起こされる事件を引き金として展開される。基本的に物語を動かす役割を怪人が担っているということだ。それは『秘密戦隊ゴレンジャー』の頃から連綿と続いてきた変わらぬ要素である。その怪人の中には階級があり、ラスボス直属の配下としての中ボスが何人か存在し、ヒーローたちは毎回やられ役の怪人たちを倒しながら、要所要所で中ボスを倒し、やがてラスボスを追い詰める。これがシリーズを通して普遍の流れなのだが、『ドンブラザーズ』には、これがない。
各話に怪人は登場するものの、それが物語を動かしていることはほとんどない。どちらかといえば、物語を動かしているのは戦隊メンバーである。メンバーの身に起こる様々な事件を面白おかしく描く。まるでシチュエーションコメディだ。これはメンバー全員が個性豊かだからこそ使える手法だとは思うが、「もしも鬼頭はるかが◯◯な状況に陥ったなら・・・」みたいなお題に従って、物語は転がる。しかもそこにヒーロー臭はほとんど感じられない。怪人は「お約束だから・・・」という程度にしか登場していない印象が強く、物語の本筋とはほとんど無関係である。
最後に戦うべき相手が未だに見えないし(元老院という存在はあるものの、それをラスボスと呼んで良いのかは不明)、敵対する組織の幹部っぽい人たち(脳人の3人)とは、戦ってはいるものの、殺し合いというよりは戯れあっているようにも見える。
だから、物語の進捗状況というのがよくわからない。この記事を書いているのが2022年12月なので、あと2ヶ月あまりで最終回を迎えるはずだというのに、終わりに向かって物語が収束しているという雰囲気が薄い。果たして本当に最終回を迎えるのか? という疑問さえ頭を掠める。
ところどころに新たな謎だったり、謎に対する答えだったりが差し込まれるが、それはかなり唐突で、取ってつけた感満載だ。
延々と続く悪ふざけの果てに、どんな最期が待っているのか。
ひょっとしたら、制作陣もその答えは未だに持っていないのかもしれない。
しかし、それこそが魅力でもあるという不思議な作品である。
申し訳程度のバトル


ドラマパートが異様に幅を利かせていることも本作の特徴である。
スーパー戦隊シリーズといえば、敵も味方も大勢での立ち回りが特徴で、そのアクションパートを見せるための繋ぎとして、ドラマパートがある、と言っても過言ではない。
しかし『ドンブラザーズ』では、アクションパートはついでのようなもので、あくまでも主要メンバーが織りなすシチュエーションコメディにこそ重きが置かれているのだ。それは時間配分を見れば一目瞭然だ。厳密に測ったわけではないけれど、ドラマパートとアクションパートの配分は、ほとんど8:2くらいの比率だ。
物語の駆動役が怪人でない、ということも手伝って、怪人それぞれが持つ特別な能力は公式サイトを見ないと理解できないものが多い。過去のスーパー戦隊をモチーフにした怪人たちは小ネタの宝庫なのだが、番組だけ観ていても名前さえよくわからないものもある。これまでのスーパー戦隊を知り尽くしている人たちには余裕かもしれないが、にわかファンや、ましてや子どもたちには想像すらできないだろう。
巨大ロボ戦は、これにさらに拍車をかける。
主人公たちがピンチになるようなシーンはほとんど皆無で、敵に何手か攻撃を繰り出させたところで必殺技で一発勝利、といった展開が多い。せっかく、脳人レイヤーなどという面白い電脳空間を設定しているというのに、そこでのやり取りは最小限。まるでイベントで横綱に次々と放り投げられる小学生力士たちを見せられているような気になってしまう。
元々、巨大ロボ戦に対して何の思い入れもない私でさえ流石に「端折りすぎじゃないか?」と思う時があるので、巨大ロボ戦こそスーパー戦隊の花形と思っている方には「つまらない」と思わせる一因となっていることは間違いない。
しかし、そんな雑な扱われ方をしているにも関わらず、巨大ロボ・ドンオニタイジンはバカ売れした様子。確かに、ふざけ倒しているくせに悔しいほどカッコいい。2022年、日本おもちゃ大賞のキャラクター・トイ部門で大賞を取ったのも納得の仕上がりである。
SNSの功罪
プロデューサーの白倉さんはかねてより「設定を固めてこぢんまりと綺麗にまとめるよりも、リアルタイムのテレビ番組ならではのライブ感を重視したい」とお考えのようで、それは本作に限ったことではなく、もっといえば白倉プロデュース作品に限ったことでもなく、今では東映作品全体がそういった空気になっている節がある。
要するに、視聴者と対話しながら展開していくということだ。ウケれば続けるし、スベれば止める。そういうキャッチボールをしながら展開を考えていくため、物語が当初の構想とは全く違う形に落ち着いてしまう可能性が高いということだ。
以前、『仮面ライダーリバイス』が急につまらなくなった理由を考察した記事を書いたが、あれも考えてみると、この「ライブ感を重視」しすぎたことが最大の要因となっているように思う。


当初はすぐに退場させるつもりだった門田ヒロミが人気者になっちゃったから継続して出演させてみる。ついでにウケたセリフをネタ化して使い回す。なんてのは、わかりやすい例だろう。だが、これによってヒロミはよくわからないモブへと身をやつしてしまう。記念写真でも撮るかのように、主要キャラクターたちに易々と変身の機会を与え、よくわからない仮面ライダーを増やし続けるなど、瞬間最大風速ばかりを気にしすぎたことも手伝って、落としどころを失ってしまったとしか思えない。個人的にも大好きなキャラクターだったし、何より仮面ライダーデモンズのデザインは最近のライダーの中では突出していると思っていただけに、残念でならない。
『ドンブラザーズ』でいえば、鬼頭はるかの変顔と、雉野つよしの心の闇は、まさに好例だろう。脇役でいえば、三度もヒトツ鬼を生み出した大野 稔や、犬塚 翼を追う刑事・狭山が準レギュラー化したのもそうだし、クールガイ・ソノイがどんどんネタキャラになっているのも同様の理由によるものに思える。
しかし、それらは本当に視聴者が望んだものだろうか? 最初はSNSなどで評判が良かったかもしれない。しかし、必要以上に視聴者のご機嫌伺いをする作品作りが良いとは思わない。本当に良いものを届けたいという作り手の気持ちは、全てに優先されるべきものである。だが現実には、視聴者の反応を見ながら作られているように見えるのが、ニチアサの作品群である(特に最近はその傾向が強いように感じられる)。
ウケたから続ける。それはわかる。どうせならバズりたいという気持ちもわかる。しかし、忘れた頃に思い出すから面白いのではないか。残り香のようなもので、ふわりと漂う香りによって、しばらく忘れていたあの人を思い出すからしんみりするのであって、いつもその香りが充満していたら、そうはならない。「懐かしの◯◯ベスト20」みたいな番組も、今、リアルタイムで目にすることのできない作品が見られるから視聴者が飛びつくのだろう。
特に、はるかの変顔はやりすぎだ。


当初は「思い切りの良い変顔をする子」として評価されていたし、それが面白くもあったが、毎回そればかりでは飽きてしまう。演じる志田さんは、様々な苦慮の中でまた新たな変顔を考案しているのだと思うが、最近はあたりまえの光景になりすぎて、観ているこちらにはほとんど響いてこない。海が見える立地が気に入って購入したマンションも、毎日飽きずに海ばかり見つめて過ごす人はほとんどいない、ということだ。
幸いにして、そもそも破綻しまくっている『ドンブラザーズ』は、ノリで物語をドライブしていっても違和感は少ないけれど、物語重視の仮面ライダーシリーズで、視聴者の反応に過剰に振り回されるのはめちゃくちゃ危険である。
「視聴者が面白がってくれたから・・・」というのが制作陣の言い訳になると考えているかもしれないが、視聴者はつまらなくなったら、あっさり手のひら返しするものだ。当初の構想通り、きちんとした物語を見せて欲しいと思っているのは私だけではないはずだ。物語を作るプロたちが視聴者に振り回されなければ、最終的に誰がみても辻褄が合わないとか、あの設定はどこ行った? なんてことにはならないとも思うし。
結論:くだらない


で、結局『ドンブラザーズ』は面白いのか? それともつまらないのか?
答えはどちらでもない。たった一言で表現すれば「くだらない」に尽きる。
「つまらない」のではない。「くだらない」のだ。
確かに上記したように、粗はある。スーパー戦隊らしくない、と言われればそれまでだが、シチュエーションコメディとしては十二分に楽しめる。
楽しめないのは、そもそも『ドンブラザーズ』の昭和っぽいノリが肌に合わないか、「スーパー戦隊シリーズ」というバイアスが外れないかのどちらかだと思う。
そもそも昭和のノリが合わないというのは相性の問題なので如何ともし難いが、これまでの「スーパー戦隊シリーズ」の既成概念に身も心も虜になっている方からすれば腹立たしさがあるのは理解できる。「こんなものスーパー戦隊などでは決してない」という意見にも頷ける。
しかし、純粋に『暴太郎戦隊ドンブラザーズ』という作品として見れば、個性豊かなキャラクターも、行きすぎた悪ノリも悪くない。
いい意味で「くだらない」。
考えてみると、これは昭和の頃のTVそのものではないか?
先述した通り、「昭和のノリが合わない」という方は一定数いらっしゃるはずだ。ネットを見ていても、「今さら昭和のノリとか古すぎる」といった意見も散見された。しかし、YouTubeなどの動画配信サイトがTVを脅かすきっかけになったのは、年々、礼儀正しくおとなしく、金太郎飴のように似たような番組ばかりが並ぶTVに対し、TVでは到底できない過激なことをする配信者たちが登場したことではなかったか。彼らは別に新しいことをしたわけではなく、昭和時代のTVでは当たり前のように行われていた破天荒なことを垂れ流していただけである。
実際、『8時だヨ!全員集合』とか『オレたちひょうきん族』などといった、昭和時代を代表するお笑い番組には、今では考えられないほどのパワーがあった。コンプラだ何だで縛られた今のTVでは決して作ることのできないヤバさがあった。たとえば、「ドキッ!女だらけの水泳大会」なんて特番では、ビキニ姿のセクシータレントさんのおっぱいポロリ映像を夕食後のゴールデンタイムに流したりしていたのだ。今みたいに「TVがつまらない」なんて意見が蔓延するなんて想像もつかないほど、TVが娯楽の王様であった時代のことである。
『ドンブラザーズ』には、それがある(おっぱいポロリは流石にない)。
制作者側が面白いと信じていることをそのまま提示してくるゴリ押し感。そこには、「つまらないと思うなら観なくても良い」というある種の割り切りがあるようにも感じられる一方で、「これが面白くないわけないだろ?」という圧倒的な自信がみなぎっている。
ふと、今自分が観ているものはスーパー戦隊シリーズではなく、『タケちゃんマン』ではないか? といった気分になったりもする(そういえば以前、犬塚 翼が“ブラックデビル”としか思えない扮装をしていたこともあった)。
「いやいや、私たちはスーパー戦隊が観たいんだよ!」という方には辛い時間かもしれない。
しかし、この徹頭徹尾ふざけ倒す作品にとってみれば、スーパー戦隊シリーズという冠さえもフリとなっているのだろう。誰もがスーパー戦隊を期待をする。ところが、このザマ(もちろん良い意味)である。そのギャップこそが、笑いのインパクトをより深めているのだろう。
とはいえ、私のようなファンからしても、観ているときは面白いけれど、後で冷静になってみると「くだらなさ」ばかりが思い出される。だが、悪くない。その「くだらなさ」にまた触れたくてつい観てしまう。そんな中毒性がある。
「ヒーローなんてね、仮面ライダーに任せておけばいいのよ」というのは、夏映画で島崎和歌子さんが演じる三枝玲子が放った『ドンブラザーズ』を象徴する一言である。
愛すべきイロモノ。
『非公認戦隊アキバレンジャー』を観るときのような気持ちで見られたら、『暴太郎戦隊ドンブラザーズ』は、きっと楽しめるはずである。「あれは公式じゃない」という批判はごもっともだが、粋じゃないぜブラザー。
最終回が終わったら、また振り返ってみたい。
それでは、ここまでお読みいただきありがとうございました。
\ 僕と握手! /