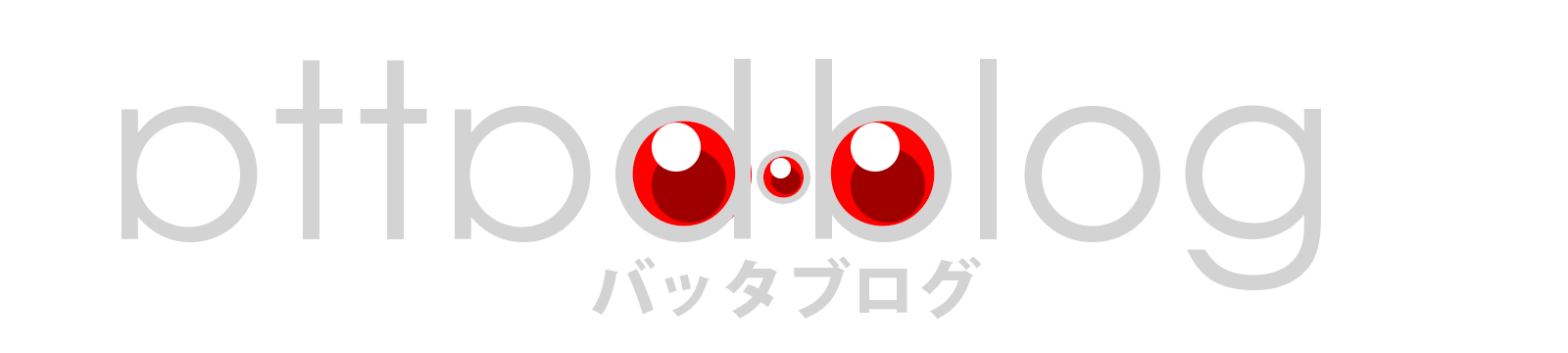1978年5月17日〜1979年3月14日まで全41話が放映された『スパイダーマン(東映)』をレビュー
『スパイダーマン』を知ってるか? と聞かれて、「知らない」と答える人はほぼいないだろう。スーパーマンやバットマンと並んで世界的に有名なヒーローの一人だ。
だが、日本版のスパイダーマンを知る人はどうだろう? まさかの巨大ロボまで登場、という日本独自の味付けをされたスパイダーマンは、放映当時、平均視聴率14%という人気番組であったにも関わらず、今では東映が運営する動画サービス「TTFC(東映特撮ファンクラブ)」でさえ視聴することのできない幻の作品である(マーベルとの版権の問題だと思われる)。
先日、この貴重な全41話を視聴する機会に恵まれた。一言でいえば最高である。当時の如何ともしがたいチープさと、そこかしこに漂う香ばしさは、旧き佳き特撮そのもの。この興奮が冷めないうちに全体的な感想をまとめておこうと思う。
なにしろ古い作品なのでネタバレ全開だが、最後までおつきあいいただければ幸いである。
あらすじと作風
オートレーサーの山城拓也は、謎の集団によって科学者である父を殺され、自身も瀕死の重傷を負う。迷い込んだ洞窟で出会ったのは、ガリアと名乗る異星人。彼は遥か銀河の彼方にある“スパイダー星”の王で、400年前に母星を滅ぼした“鉄十字団”という組織を追って地球へやってきたものの、彼らの罠によって洞窟に幽閉されていたらしい。
ガリアが、瀕死の拓也に“スパイダーエキス”と呼ばれる謎の液体を注入すると、奇跡的な回復力で拓也は一命を取り留める。スパイダーエキスにはスパイダー星人の持つクモの力が込められており、これによって拓也は超人的な力を得ることになる。さらにガリアは拓也に謎のブレスレットを託し、スパイダーマンとして、鉄十字団を率いるモンスター教授を倒して欲しいと依頼する。
殺された父と、ガリアの積年の恨みを晴らすため、拓也はスパイダーマンとなってモンスター教授が率いる鉄十字団と戦う、というのが、あらすじである。
この幽閉されていたガリアという人が、クモの力を持つスパイダー星の王なのに、地球の洞窟に生息していた毒蜘蛛の猛毒に苦しんだという謎の設定からして香ばしい。さらに言えば、400年前に地球に持ち込んだ“宇宙戦艦マーベラー”が、400年後の今、モンスター教授が作り出す最新鋭の怪人たち(マシーンベムと呼ばれる)を圧倒するというのも凄い話だ。火縄銃で最新鋭のライフルと渡り合うようなものではないのか。
そしてネーミングも絶妙にダサい。ラスボスがモンスター教授で、女幹部がアマゾネス。とりあえず横文字多めで、『スパイダーマン』が生まれたアメリカに少し寄せてるのかなと思いきや、軍団名は鉄十字団。このイカれたセンスもまた最高だ。
1話完結のオムニバスとなっており、鉄十字団が企む悪事をスパイダーマンが打ち砕くというテンプレで進むのは、いつもの特撮だが、子ども向け番組としては異例なほど社会派というか、シリアスなメッセージも込められており、その点も人気だったのは、今ではタブー視されそうな薬物関係なども扱った『快傑ズバット』を彷彿とさせる。
アメリカ製スーツに刻まれた和の心
主人公の山城拓也は、左腕に装着したブレスレットを操作してスパイダーマンへと変身するが、この変身がショボい。操作すると、どこからともなく現れる(貼り付けられているようにも見える)全身タイツを身にまとい(設定では、ブレスレットに収納されているらしい)、背中側の両肩に渡るファスナーを閉じれば変身完了となる。
この全身タイツは、スパイダープロテクターと呼ばれる。何しろドンキで売られている全身タイツみたいな生地なので、全く守られている感じはしないが、本家スパイダーマンも正体を隠すためだけに着込んでいたはずなので、この点は仕方ないだろう。全身タイツと聞くと、つい“モジモジくん”などを思い出してしまうのだが、全体的なデザインは本家を踏襲しており、今見ても十分にカッコいい。ただ、胸に描かれたクモのマークは本家と明らかに異なる。1962年に誕生したスパイダーマンの胸のマークは、今もちょいちょい変わっているのだが、そのどれとも違うテイストだ。
まるで子どもに書かせたような間違ったクモ感とチープさが特徴で、一度気になり出すとクセになる。
能力も基本的には本家同様、クモの力を使うのだが、これらにもチープさが漂う。例えば、東映版は“スパイダー感覚”という、これも絶妙に微妙なネーミングの探知能力によって鉄十字団の動きを察知する。物語の途中からは、FBIと協力したり、無線を使ったりし始めるのだが、基本的には自分の直感を大事にするタイプのようだ。
また、手から放つクモの糸“スパイダーストリングス”は、どう見ても縄だ。スパイダーストリングスにぶら下がり、ターザンのようにビルからビルへ、木から木へといった移動をするシーンが度々登場するが、完全に縄である。もうひとつ、クモの巣のような網を放って複数の戦闘員たちを絡めとる“スパイダーネット”という武器もあるが、これはただの投網である。
そんな数ある能力の中で最もシュールなのが壁歩き(?)のシーンだ。クモらしく壁や天井を縦横無尽に這いずり回ることができるため、高層ビルやダムの壁など、簡単に忍び込めないようなところにも難なく潜り込むことができてしまうのだが、スパイダーマンはこの能力を何故か戦闘中も頻繁に行ってしまうのだ。
これが屋外での戦闘で、目にも止まらぬ速さで壁を登って敵の攻撃を避ける、というなら全然アリだと思うのだが、一般住宅の室内で、敵も手を伸ばせば届く程度の天井に張り付いていたスパイダーマンが、のろのろと壁を伝って降りてくるのを戦闘員たちが全員で見守っていたりするのだから笑ってしまう。
今見ると、何ともマヌケに見えてしまうこれらの映像だが、原作者スタン・リーさんは、「スパイダーマンらしいアクションとスピード感が再現されており、世界各国で制作されたスパイダーマンの中でも東映版は別格」と好意的に評価していたことが知られている。その前年からアメリカでもTVドラマ化されていたため、それと比較してこき下ろされてもおかしくはなかったところを、単なる二番煎じではなく、日本独自の味付けをしたのが良かったのだろうと思われる。日本の特撮ファンにとっては、ちょっと鼻の高い出来事だ。
特撮の歴史に残る名乗り
本家は絶対にやらないことだが、この東映版スパイダーマンも、日本の他のヒーロー同様に名乗りを上げる(そういえば、ウルトラマンは名乗りを上げないので、名乗りを上げるのは東映特撮の特徴なのかもしれない)。そして、この名乗りのシーンもまた東映版スパイダーマンを特別なものにしているのだ。以下に、それらの名乗りを書き連ねてみたいと思う。
「地獄からの使者、スパイダーマン」
「地獄から来た男、スパイダーマン」
「鉄十字キラー、スパイダーマン」
「親の愛に泣く男、スパイダーマン」
「復讐に燃える男、スパイダーマン」
「約束に命をかける男、スパイダーマン」
「犬笛に咽び泣く男、スパイダーマン」
「冷血動物マシーンベム殺し、スパイダーマン」
「母と子の愛の絆を守る男、スパイダーマン」
「モンスター退治の専門家、スパイダーマン」
「血は人間の絆、愛の証。愛のために血を流す男、スパイダーマン」
「情け無用の男、スパイダーマン」
「家なき子どもたちのために涙を流す男、スパイダーマン」
「少年の友だち、スパイダーマン」
「悪のカラクリを粉砕する男、スパイダーマン」
「物言わぬ動物の愛に泣く男、スパイダーマン」
「親の心、子の心、大切な心を守る、スパイダーマン」
「爆弾魔を退治しに来た男、スパイダーマン」
「亡き兄に復讐を誓う兄弟に心を打たれる男、スパイダーマン」
「キノコ狩りの男、スパイダーマン」
「大東京の停電を阻止する男、スパイダーマン」
「野生の少女に味方する男、スパイダーマン」
「カメラのレンズは真実を見る瞳。曇りなき瞳を信じる男、スパイダーマン」
「少年の勇気に希望を見た男、スパイダーマン」
「不死身の男、スパイダーマン」
「孤独な少年のために戦う男、スパイダーマン」
「100m先に落ちた針の音をも聞き取る男、スパイダーマン」
「少年探偵団の友情を信じる男、スパイダーマン」
「格闘技世界チャンピオン、スパイダーマン」
ご覧の通り、かなりのバリエーションが存在する。当初は「地獄からの使者」ばかりだったが、視聴者を飽きさせないように、という配慮なのか何なのか、徐々に違う名乗りを上げ出し、中には完全にネタとしか思えないものも存在する。特に「犬笛に咽び泣く男」には最優秀賞を差し上げたい。これらの名乗りは、今なおネタとしてまとめ動画としてアップされているものも存在するので、気になる方は探してみても良いかもしれない。動画で見ると、独特な口上の面白さに加え、やけにくどい身振り(ただしキレは抜群)もまたクセになるはずだ。
巨大ロボットの登場
東映版スパイダーマンを語る上で絶対に外せないのが、巨大変形ロボ・レオパルドンの存在である。
東映版スパイダーマンには、普段の移動用として“スパイダーマシンGP-7”という名のオープンカーが存在する。そこかしこにクモっぽいモチーフを散りばめている(ノーズ部分にはクモのアゴ、ボディサイドには左右各4本ずつ突き出したエグゾーストパイプなど)が、これまで東映特撮に登場した主人公専用マシンの中でも屈指のダサさを誇ると個人的には思っている。空陸両用という、まるで『快傑ズバット』に登場したズバッカーのような性能で(デザイン的にはあちらの方が相当カッコいい)、宇宙戦闘艦マーベラーへの搭乗時にも使われる。
スパイダーマンの版権を持っているマーベルにインスパイアされたと思しき、このマーベラーという宇宙戦闘艦は、スパイダーマンの「チェンジ!レオパルドン!」の一言で、巨大ロボ・レオパルドンに変形する。
今見るとどうってことないデザインだが、当時はめちゃくちゃカッコ良く見えたものだ。巨大戦艦が巨大ロボに変形するというのも胸熱で、キッズたちはレオパルドンに心を鷲掴みにされた。そこに変形を完全再現できる超合金が発売されたのだから売れないわけがない。実際、当時の特撮関連グッズの売り上げとしては、史上空前と言われるほどの大ヒットとなった。
ただし作中での扱いとしては、変形して登場するところまでがクライマックスで、レオパルドンと巨大化したマシーンベムとの立ち回りはほとんどなかった。ゆえにピンチに陥るようなことは最後まで一度もなかった。このあたりは、その後のスーパー戦隊シリーズとはだいぶ異なる。
巨大化したマシーンベムに対抗するため、左手首のブレスレットに向かって「マーベラー!」と呼びかけた時点で勝ち確。変形後、申し訳程度に攻撃を加えたところで「レオパルドン・ソードビッカー!」の掛け声と共に、右足に格納されたソードビッカーという剣を投げつけて敵を倒す。「(長くて立派な剣なのに)斬らないんだ?」とツッコミを入れる人は多かったはずだ。
後年、マーベルのコミックの中にこのレオパルドンが登場したことが大きな話題になったことを覚えているファンも多いことだろう。
今のスーパー戦隊シリーズの礎となった作品
『スパイダーマン』が大成功に終わった後、登場した新ヒーローが『バトルフィーバーJ』である。
現在では、スーパー戦隊シリーズの第3作目として認知されている本作だが、当時そのような括りはなく(“戦隊”という言葉はどこにもない)、単にマーベルと東映の協力関係の中で生み出された作品となっている。紅一点のミスアメリカ(名前だけはマーベルのキャラクターだが、デザインには手を加えられている)を除く4人は東映オリジナルキャラということで、『スパイダーマン』とはだいぶ毛色が違うが、『スパイダーマン』からの影響をモロに受けた作風となっている。
何といっても、巨大ロボが登場するところにレオパルドン・ショックの大きさが窺える。ヒーローと巨大ロボの組み合わせがウケることは実証済みである。スポンサーとなる玩具メーカーのことを考えても、二匹目のドジョウを狙いたくなるのは当然のことだったと言える。
ただ、レオパルドンの影響が大きすぎたのか、バトルフィーバーロボの必殺技が「レオパルドン・ソードビッカー」を二刀流にしただけの「クロスフィーバー」だったのは流石にやりすぎだったのではないかと思う。後に、「電光剣」という巨大な日本刀を振るうことにはなるのだが、これがなければ、本当に『スパイダーマン』の二番煎じになっていたのでは? と思う。オープニング曲のイントロも『スパイダーマン』と『バトルフィーバーJ』は驚くほどテイストが似ているし。
兎にも角にも、この『バトルフィーバーJ』の成功によって、翌年の『電子戦隊デンジマン』から今に続くスーパー戦隊シリーズが生まれたのだ。現在のスーパー戦隊シリーズの礎を築いたのは『バトルフィーバーJ』と言って良いが、その『バトルフィーバーJ』を生み出したのは、『秘密戦隊ゴレンジャー』でも『ジャッカー電撃隊』でもなく、『スパイダーマン』だったのは間違いのない事実だ。そもそも『ゴレンジャー』や『ジャッカー』は90年代までスーパー戦隊シリーズに組み込まれてさえいなかったのだから。
『スパイダーマン』無くしてスーパー戦隊シリーズはあらず。
東映版『スパイダーマン』という伝説の作品は、日本の特撮史のひとつの礎でもあるのだ。もしも幸運にも観る機会に恵まれたなら、何を差し置いても観てみることをオススメする。
それでは、ここまでお読みいただきありがとうございました。
\ 僕と握手! /