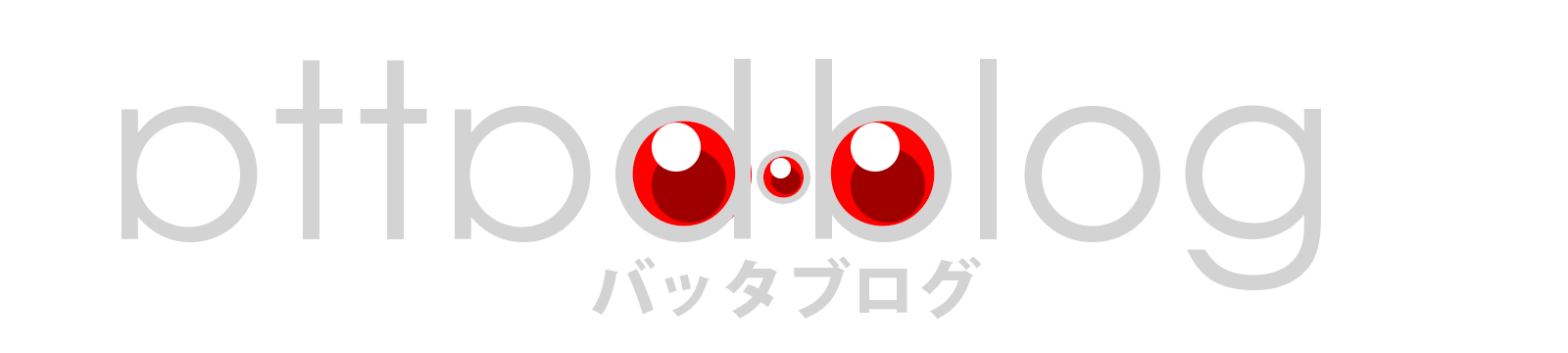特撮ヒーローが好きだ。
この想いは子ども時代から1ミリも変わらない。だが、すっかり大人になった今、この想いをリアルで口にすることはほとんどゼロだ。それはちょっと恥ずかしいからである。
勘違いして欲しくないのは、特撮作品が恥ずかしいものだと言っているつもりは全然なくて、あくまでも自分の中の意識の問題である。『トクサツガガガ』というマンガがあったが、まさにあんな感じで、いつまでも特撮ヒーローに胸を焦がす自分を曝け出すことに抵抗があるのだ。
いつの間にか自分のことを「オタクだ」と公言するのが普通の世の中になっているが、私はTVで宅 八郎さんがイジり倒されるのを見てきた世代だ。毎年、コミケのために東京ビッグサイトに何万人集まった、なんてことがニュースになっていても、やっぱりオタク趣味というのは、どこか日陰者のそれなのだという意識が消えない。その晴らせない鬱憤を、こうしてブログにぶつけている節さえある。いわゆるムッツリスケベだ。
「こんな子どもじみたものに熱を上げるのはもうやめよう」と思った時期もあったが無理だった。ラジオなどから特ソンが流れてくれば、無条件に体温が2℃くらい上がったような気分になるし、“ライダー”とか“レンジャー”みたいな単語には秒で反応してしまう。
私がスポンジで、特撮ヒーローが水ならば、時間と共にその記憶は蒸発してキレイさっぱり消えてしまうかもしれない。しかし、私にとって特撮ヒーローとは水ではなく、既にスポンジ(細胞)の一部である。どれだけ乾かしても、絞っても、特撮ヒーローへの憧れが枯れ果てることはないだろう。
では、いつまでも消えることのないこの想いの根源は何なのか? 特に、大人の心を鷲掴みにして離さない特撮ヒーローの魅力について私なりに考えてみたい。最後までおつきあいいただければ幸いだ。
胸熱要素満載
まずは何と言っても、胸熱であることだ。
カッコいいデザイン、目を奪われるアクション、ド派手な演出。これらは子どもたちだけでなく、大人にとってもわかりやすい要素だ。しかもこれらは、子どもたちにとっては単に「カッコいい!」くらいのものであっても、大人になると更に味わいが増すものである。
まずデザインだが、隅から隅まで、かなり綿密に考えられていることは、大人になればなるほど、特撮の歴史を知れば知るほど理解できる。モチーフや意図などがわかると、そこまで考えてデザインされていたのか! と驚かされることもしばしばである。予算を削るために既出のヒーローや怪人のスーツを改造したなんて裏話も出てくるが、こんな情報だって興味深く楽しめるのが大人である。そういう裏事情がわかると、「あれ? ひょっとしてコレも◯◯の流用か?」なんて見方もできるようになり、それもまた楽しかったりする。
さらにストーリーも胸熱だ。誰かの危機を救うヒーローとか、絶体絶命のピンチを乗り越えるヒーローというフォーマットは昔ながらのデフォだが、老若男女を問わず理解されやすい。王道とも言える展開によって、ジェットコースターのように我々視聴者の感情は喜怒哀楽あらゆる方向に振り回される。王道とマンネリは背中合わせだが、シェイクスピアの時代には、とうに物語のフォーマットは出尽くしたとさえ言われているのだから、全体的な流れに対して「またか」とか「古臭い」なんて感想を述べるのは野暮である。
それよりも重要なのは描写する内容の深さである。実は昔から特撮作品というのは、意外と深いテーマを抱えていたのだが、TV業界で「ジャリ番(子ども向け番組という意味)と呼ばれていたように、当時の特撮は、あくまでも子ども向けとカテゴライズされていた。そのため、そこに流れる深いテーマはサラッと流す程度で、「世界征服がー」「日本征服がー」「四国制圧がー」と、わかりやすい側面ばかりを押し出していたのだ。これは特撮に限らずアニメにも言えることで、例えば永井 豪先生の『デビルマン』が良い例だ。アニメではヒーローものという側面ばかりを強調しており、作品に込められた薄暗さは、結末まで含めてほとんど割愛されていた。原作を読んだことのある人ならおわかりの通り、原作とアニメは全くの別物である。アニメでは幼稚な印象しかなかったという人も、原作を読めば印象は180度変わるはずだ。今読んでもその印象は全く変わらない。歴史に残る名作である。
これと同じことが特撮にも言える。当時の特撮しか知らず、「特撮は子どもの観るもの」と決めつけている人たちが、今の特撮を観たら間違いなく驚くはずだ。正義のヒーローと悪の組織という対立構造は変わらぬお約束だが、善と悪とのせめぎ合いという単純な展開に終始していた特撮は影をひそめ、時に何が善で何が悪なのかさえ不確かな人間ドラマがそこにあるからだ。特に『仮面ライダー』シリーズにおいて顕著だが、2000年の『仮面ライダークウガ』以降、これまでのように1話完結の物語を最終回まで続けるという時代劇スタイルを捨て、1本の物語を細切れに見せる大河ドラマスタイルへと変貌している。これによって、これまでは『アンパンマン』などと同列に語られがちだった特撮ヒーローが、『名探偵コナン』くらいには対象年齢がアップした印象だ。人物描写は深みを増し、悪党の背景さえ透けて見えるようになった。
これは感情を揺さぶられるポイントが増えたということでもある。昔の特撮では、悪に蹂躙された一般市民の心情を思って泣きそうになるとか、それに対して怒りを燃やすヒーローに同調するとか、共感できるポイントはその程度だったが、今は悪の立場にいる登場人物の過去を知って同情したりできてしまうのだから驚く他ない。規模は比べるべくもないが、ヒーローの世界標準と言えそうなマーベルの作品に近づいた、と言えなくもないような気もしている。個人的にはマーベルの作品よりも日本の特撮が圧倒的に好みだが、より多くの人たちに届きやすい作品になっている、とは言えるだろう。
ただし、物語の描き方という点について驚くというのは、おそらく昭和世代の人たちであって、1990年代後半(エヴァ以降と言っても良いかもしれない)の特撮に少しでも触れたことのある人なら、それについては「もう知ってる」という状態だと思われる。
だが、アクションや演出は違う。ワイヤーやCG、さらには撮影機材の進歩によって、とんでもない進化を遂げている。仮に10年ほども最近の特撮を観ることのなかった人たちなら、その進化に驚くはずだ。特にCGは隔世の感さえある。スーパー戦隊シリーズ最新作『王様戦隊キングオージャー』を観て欲しい。パッと見では、いったいどれがCGでどれが作りものなのか見分けがつかないほどのクオリティを誇る。もちろん、最新映画などと比べれば差はあるだろうが、予算が少ないことで有名なニチアサでさえ、これほどの映像を提供できることには舌を巻く。2000年前後あたりの特撮で使われていた、“いかにも”なCGは見る影もない。当時、子ども時代を送った人たちが今の特撮を観たら驚愕するはずだ。「これが今の特撮か」と。
このように、子どもだけではなく大人をも容赦なく引き摺り込むだけの胸熱要素てんこ盛り。これがウケないわけがない。
3次元ならではのライブ感
特撮作品の魅力として、実写によるライブ感も外せない。
今更言うまでもなく、特撮作品は作りものだ。ヒーローも悪党も、だいたいみんな被りものである。だが、その被りものに命を与えているのは演者の肉体であり、これは紛れもないリアル。ヒーローのアクションがカッコいいのは、演者がカッコいいアクションを実際にこなしているからだ。
しかし、リアルゆえの不完全さもある。パンチやキックを例えに出せば、実際に当ててはいない。アクシデントとして当たってしまうことはあっても、毎回実際にぶん殴っていたら、やられ役は身体がもたないだろう。あくまでも当てているフリ、当てられたフリをしているだけだ。だからそこに不完全さが生まれる。繰り出したパンチの角度によって、或いはリアクションの一瞬の遅れなどによって、ほんのちょっとの嘘臭さが顔を出す。
これがアニメならまるで異なる。全てが虚構だ。その代わり、実写では到底できないようなアクションもお手のものである。例えば『ドラゴンボール』などで見られた一瞬で相手の背後を取る動きや、空中でパンチやキックの応酬をするシーンなどは、未だにアニメの得意分野だ。また、殴る蹴るだけでなく、刀で斬った斬られたなんてことも絵だったらどうとでも表現できる。キャラクターの怪我を心配して、フリをさせる必要がないからだ。
このように、アニメやCGなら造作もなくできる表現を演者の肉体でできる限りの表現をする。そこには先述した通り、ある意味の嘘臭さも漂うのだが、生々しさは圧倒的にこちらの方が上だ。実存する肉体が見せる生の動きこそが、嘘だらけの虚構の世界に唯一真実をもたらす。
マンガでもアニメでも、人の心を惹きつけるのは、そこに込められたリアルだ。舞台が異世界や今ではない古の時代など、どれほど現実とかけ離れた世界設定であっても、そこに人間として変わらぬリアルが何かあれば人は共感できる。多くの場合、それは感情だろうが、肉体もまた同様の効果を生んでいる。単に実在する人が演じているというだけで、世界そのものもまた実在するように感じてしまう。アニメはどこまで行ってもアニメだが、実写にはほんのりと現実とクロスオーバーする瞬間があるのはそのためだろう。
完璧に作り手の意図通りの動きを実現できるアニメではあり得ない、多少のズレ。それこそが現実であり、その予想できなさが生む意外性の面白さ。それは扇風機が規則正しく吐き出す強風よりも、不意に頬を撫でる微風に心地よさを感じる感覚に似ている。
役者に魅了される
また、登場人物を演じるのが現実に存在する役者さんであることも大きな要素だろう。
しかも主要キャラを担当するのは20歳前後の若手がほとんど。過去を振り返っても、30代以上で主要キャラを演じた役者さんというのは数える程しかいない。
1990年代までは、特撮作品はやはり子ども番組という認識であり、そこに出演してしまうといつまでもその色から抜け出せなくなる、ということで、芸能事務所は自分たちの金の卵をそんなところにできれば出してくない、と考えていたようだし、仮に出したとて、その後はプロフィールから抹消してしまうケースも多かった。
ブレイクスルーとなったのは、2000年の『仮面ライダークウガ』である。主演のオダギリジョーさんは、この作品によってその名を世に知らしめ、人気俳優となった。
続く『仮面ライダーアギト』に出演した要 潤さんも人気俳優となったことで、平成ライダーは“若手俳優の登竜門”とさえ言われるようになった。
事実、その後は水嶋ヒロさん、佐藤 健さん、菅田将暉さん、福士蒼汰さん、竹内涼真さんなど(全て主演俳優のみ抜粋)、多くの人気俳優が『仮面ライダー』をきっかけに羽ばたいている。
ここではライダーシリーズを例に挙げたが、松坂桃李さんや横浜流星さんはスーパー戦隊シリーズ出身である。
こうしたイケメン揃いのため、いつしか特撮ヒーローは、「子どもよりも主婦がハマる」などと言われるようになった。それまでは子どもたちと一部のオタクのもの、みたいな捉え方をされていた特撮作品は、女性ファンをも獲得するようになったのである。
さらに言えば、日本の3大特撮と言われる『ウルトラマン』、『仮面ライダー』、『スーパー戦隊』のうち、『ウルトラマン』を除く2つのシリーズ作品では、基本的に1年間という放送期間が約束されている。これだけの長期間に亘って放送されるドラマというのは、NHK大河と特撮くらいのもの。この期間に何が起こるかと言えば、役者さんの進化である。演技経験の浅い若手俳優が、1年間という期間を通じてめきめきと力をつけていく様子は、我が子や親戚の子どもの成長を見守るような気持ちになり、愛着も湧く。すると、作品が終了しても、その役者さんの動向が気になる。つまりファンになっているのだ。
その役者さんたちも、最近ではキャリアを隠すことはあまりない。作品が終了して何年も経ってから、その作品への愛を口にする人も多い。映画の舞台挨拶など、上映されているタイミングで愛を語るのはただのプロモーションに過ぎないが、過去に想いを馳せて語られる作品愛だとか熱というのは、それを観てきた人の胸を熱くさせる。
2018年に公開された劇場版『平成仮面ライダー20作記念 仮面ライダー平成ジェネレーションズ FOREVER』に、10年ぶりに佐藤 健さんが出演し、「僕の原点」と発言したことは記憶に新しい。これによって何が起こるかと言えば、ライダーのことなど知らない佐藤 健さんのファンが『仮面ライダー電王』に手を出してハマるとか、当時『電王』は観ていたが、最近のライダーには興味のなかった人たちが再びライダーにハマるきっかけになるといった現象が起こる。
大人が特撮沼にハマるきっかけは、案外こんなものだったりもするのだ。
香ばしさ
大人が特撮にハマる3つ目の要素として挙げたいのが、“香ばしさ”である。
ここまでご紹介してきた“胸熱”だとか“生々しさ”なんて要素は、味覚に例えれば“甘い”とか“辛い”といったものに近い。要するに、子どもでもわかる、というものだ。
しかし、特撮の魅力はそれだけに止まらない。酸いも甘いも嗅ぎ分けたからこそ分かるものもある。それが“香ばしさ”である。
映像そのものにも香ばしさが漂うのだが、これは当時の映像技術と子ども向け番組ならではの低予算ゆえのことなので、流石にケチをつけるのは大人げない。手書きの効果線、釣り糸がくっきり見える空中戦、崖下へと落下するあからさまな人形などなど。例えるなら、デパートの屋上で繰り広げられるヒーローショーにケチをつけるようなものである。
それよりも、設定や演出、さらに物語のぶっ飛び具合にこそ、真の香ばしさがある。
設定がコロコロ変わったことで有名なのは、『スパイダーマン(東映版)』に登場した女性幹部アマゾネスだろう。作中で、コスチュームだけでなく、髪の色まで変わるという迷走ぶりを見せた。
また、演出として例に挙げたいのは、『秘密戦隊ゴレンジャー』と『バトルフィーバーJ』である。スーパー戦隊といえば名乗りのシーンは重要だが、『ゴレンジャー』は途中まで「5人揃って、ゴレンジャー!」と名乗る際、5人縦並びで、手をじゃんけんのパーの形にして前に突き出すという、今見ると何ともダサいポーズを決めていた。さらに酷いのが『バトルフィーバーJ』のバトルフランスである。名乗りの際、フラメンコのように顔の横で両手を何度か叩くポーズを見せるのだが、何故か顔が小刻みに揺れている。随分昔、ダウンタウンの松本人志さんがネタにしていたような記憶もあるのだが、勘違いかもしれない。そもそもフランスなのにフラメンコって何だよ? というツッコミは置いておくが、スタッフ間で「変だよ」という意見が出たのか、どちらも番組途中で改められている。『ゴレンジャー』は今のスーパー戦隊の礎とも言える横並びの名乗りに変わった(それでも最終形に至るまでには何パターンか試されている)し、バトルフランスの顔の揺れは少しおとなしくなった。
さらに、ぶっ飛んだ展開もまた香ばしい。例えば『仮面ライダー』では、世界征服を企むショッカーが唐突に「四国を制圧する」などと言い出したり(スポンサーの兼ね合い。昔の特撮ではホテルの宣伝などでよくあった)、怪人ヒルゲリラによって血を吸われて奴隷人間になってしまった一文字隼人を救うために薬品を投与するのが、まさかの経口取得(ヒルゲリラは血を吸って薬品を注入することで人間を奴隷に変えてしまう。ならばそれを治すための薬品は注入するのが普通なのでは?)だったり、といったことがあった。こういった「なんでそうなった?」と、視聴者を置き去りにするような展開が多かった。
このぶっ飛び具合を逆手に取ったのが名作『快傑ズバット』である。特撮ヒーローのぶっ飛んだ要素をこれでもかと放り込んだ寄せ鍋のような作品だった。そのシュールな作風は、未だ格別の香ばしさを放っている。
最近の特撮作品には、正直、これほどの香ばしさは感じられないが、それでもどこか論理的なところをすっ飛ばして「え? 何で?」みたいな部分は全然ある。こういった冷静に考えたらおかしい部分に目くじらを立てるのではなく、ほくそ笑みながら眺めてみるのが大人というものだろう。
醒めない夢
『醒めない』という曲がある。私が大好きなバンド・スピッツの作品だ。
その歌詞の中に「最初ガーンとなったあのメモリーに今も温められてる」というフレーズがあるのだが、これがやけにしっくりくる。ジャンルを問わず、鮮烈な原体験はいつまで経っても消えることはない。それが草野正宗さんにとってはロックだったのだろうし、私にとっては特撮ヒーローだったということである。
上記したいくつかのポイントに「ガーンとなった」人たちが今も特撮にハマっているのだろう。そして、音楽と同様、特撮も年々アップデートされている。しかもそれをアップデートしているのは、子ども時代にそのシリーズが好きだったという人たちだったりするのだ。変わらぬ愛と、最新の技術によって生み出される作品たちは、子どもたちだけでなく、そのクリエイターたちと同世代の心にもしっかり刺さるはずだ。
こうして、彼らの醒めない夢は、私たちにとっても醒めない夢であり続けている。色々と書き綴ってきたが、本当の答えは、そんなシンプルなものでしかないのかもしれない。
それでは、最後までお読みいただきありがとうございました。
\ 僕と握手! /