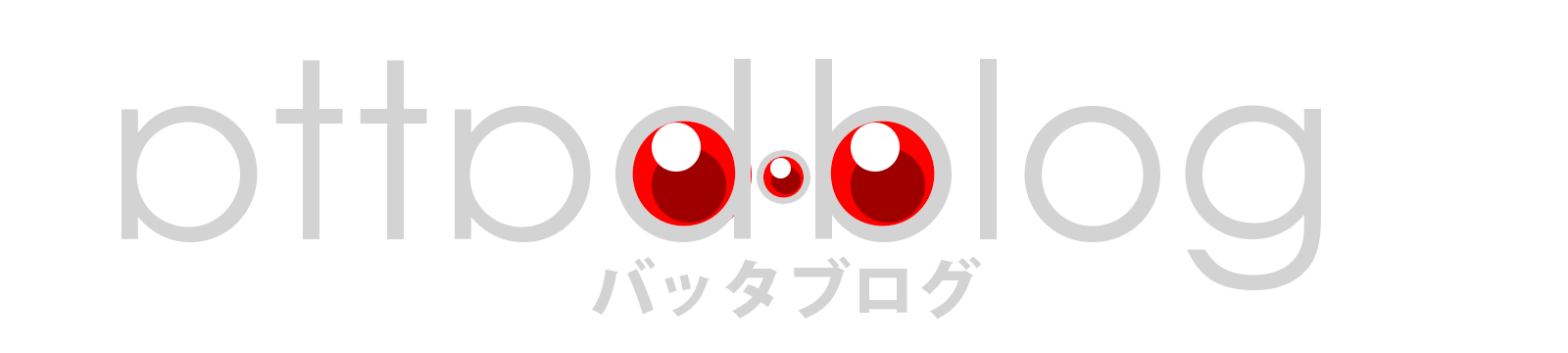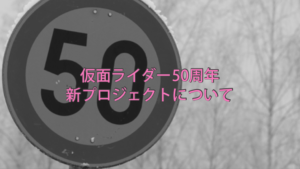2023年3月17日公開『シン・仮面ライダー』(監督・脚本:庵野秀明)
2021年4月3日、仮面ライダー生誕50周年を祝して3つの作品が制作されることが発表された。そのひとつが『シン・仮面ライダー』である。タイトルに『シン』の名を冠するところからもわかるように、庵野秀明さんが関わっている“シン・ジャパン・ヒーローズ・ユニバース”の1作であり、『シン・ゴジラ』『シン・エヴァンゲリオン劇場版』『シン・ウルトラマン』に次ぐ『シン』シリーズ4作目。そして、先に挙げた仮面ライダー生誕50周年の大トリを飾る作品でもある。
2022年10月28日に、仮面ライダー生誕50周年記念作第2弾(第1弾はアニメ版『風都探偵』)として、シリーズ屈指の人気作『仮面ライダーBLACK』をリブートした『仮面ライダーBLACK SUN』がAmazonプライムビデオで独占配信されたが、5点満点中2.75点(2023年3月時点)という、まさかの低評価を叩き出してしまったのは記憶に新しい。私個人はつまらないとは思わなかったが、世の多くのライダーファンがガッカリしたのは事実のようだ。そんなこともあって、『シン・仮面ライダー』はファンにとって、まさに“最後の希望”となっていた節もある。公開日が決まり、その日が近づくにつれ、SNSは大いに盛り上がりを見せた。
ところが、である。
公開後、SNSにはファンたちからの、なんとも微妙な感想がアップされることになる。『仮面ライダーBLACK SUN』ほど否定的なものは少ないし、むしろ熱狂的に肯定的な意見も多い中で、否定はしないながらも「敷居が高く、観る人を限定する」といった、やけに冷静なファンの感想は、一際真実味を帯びているように見えてしまう。これは、「誰がなんと言おうと観に行く!」と鼻息の荒いファンは別として、劇場に足を運ぼうかどうかと迷っている人たちにとってはマイナス要素でしかない。やはり、みんなが観たいのは、「興行収入No.1」とか「全米が泣いた!」といった、誰が観ても面白いと思える作品なのである。実際、興行的には、かなり期待外れのようで、東映は必死のプロモーション活動に追われている。
だが、これは本当に観る価値のない作品なのだろうか?
視聴後、確かに100点満点とは言えなかったけれど、個人的には大満足の仕上がりだったと言って良い。劇場でひっそりと泣きそうになったりもしていた。他人に勧められるか? と問われれば、全力でお勧めしたい。
その一方で、本作が思ったほどの興行成績を残せていない理由もわかった気がする。そこで本記事では、一切の忖度なしに、評価が微妙な理由と、私の正直な感想を綴ってみたい。ネタバレは極力しないので、まだご覧になっていない方も安心して最後までおつきあいいただきたい。
なお、私は面白いという意見もつまらないという意見も両方あって然るべきだと思うし、どちらかが正しくてどちらかが間違っているとは決して思わない。それと同様に、ここに書いたのは、あくまでも私個人の感想でしかない。反対意見もあるだろうが、こういう考え方もあるんだ、くらいに眺めていただければ幸いである。
地味
『シン・仮面ライダー』の感想を見ていると、必ず出てくるのが「CGがショボい」といった批判である。
確かにハリウッドなど海外の超大作とは比べるまでもないし、普段から最新のゲームなどを見慣れていれば、地味であることは間違いない。だが、これは本質的な部分では全くない。CGが盛り上がってきた1990年代には、映画の売り文句の一つとして「全米No.1!」などと同様に「最新のVFXを駆使したド迫力の映像!」といった文字が踊っていた。これまでに見たこともないような映像を見せてあげる、というのだ。その言葉に嘘はなく、かつて見たこともないような、もしくは現実には簡単に見ることのできない世界が鮮やかに描かれていた。だが、それらの作品が全て面白かったわけではない。見た目が派手だっただけである。
見た目が派手だから面白いわけでないことは、映画に限らず、ゲームを見てもわかる。4Kで細密に描かれた美しいグラフィックの大作ゲームをリリースするプレイステーションやX-boxといった高性能を謳うハードを絶賛し、それらと比べて明らかに低性能な任天堂のハードをゴミと罵る人たちがいる。確かに、どうせならグラフィックは美しい方が良い。しかし、ハマるゲームというものが、全て大作ゲームかと言われれば、そうでもない。私なども、最近はニンテンドースイッチの『スプラトゥーン3』に親子共々ハマりまくっている。やはり重要なポイントは、見た目でなく、楽しさという本質を捉えているかどうかだろう。
それは世界で一番売れたゲームである「マインクラフト」を見ても明らかだ。本作で描かれているのは、全てが四角で作られた古臭ささえ感じる世界である。PCやプレイステーション、X-boxはもちろん、ニンテンドースイッチなどでも遊べるが、そこに高性能ハードの優位性を感じることはほとんどない(処理能力は除く)。そもそもアップデートを重ねているとはいえ、11年も前に発売された作品である。最新のゲームと比べてショボい部分があることは否めない(あえてチープな見た目を与えられたことによって、劣化がわかりづらいというのはあるかもしれない)。それでも、この移り変わりの早すぎる世界において、10年以上もの長い間、多くの人に愛され、プレイされ続けているのは奇跡的である。それは純粋に「面白い」からだろう。
『シン・仮面ライダー』に話を戻せば、TVではなく映画なのだから、それ相応の映像を見せて欲しいという気持ちはわかる。しかし、映画もまたCGの良し悪しだけで語られるべきものでないはずだ。だからこそ、本作を観ようかどうかと迷っている方は、「CGがショボい」なんて意見だけで「行かない」なんて判断をして欲しくはないと切に願うのだ。
しかし、『シン・仮面ライダー』が“地味”に見えてしまうのは間違いない。それは他のシン・シリーズと比べても明らかだ。ただしこれには理由がある。『シン・ゴジラ』『シン・エヴァンゲリオン』『シン・ウルトラマン』を思い出して欲しい。そこに登場して暴れ回っていたのは、巨大な怪獣や宇宙人、はたまた汎用人型決戦兵器である。“巨大”というのは、それだけで派手である。ミニチュアの街を壊して回るだけで見栄えがする。しかもビームまで放つのだ。庵野さんといえば、若い頃に宮崎 駿監督の名作『風の谷のナウシカ』で巨神兵がビームを放ち、目の前のものを焼き払うシーンを描いたことでも有名なビームの名手(?)。あの独特の間の取り方は震えるほどカッコ良い。その表現は、エヴァはもちろん、ゴジラの火炎放射能やウルトラマンのスペシウム光線にもしっかりと受け継がれていた。その1シーンを見せられただけで、観客は「良いものを見た」感に包まれるはずだ。
ところが、本作に登場するのは我々と同じ人間サイズのオーグメントと呼ばれる怪人たち。主人公はバッタの力を持つバッタオーグ。しかも、初代仮面ライダーのリブートということで、平成以降のライダーのように武器を振り回したりもしない。ビームなど以ての外で、バッタ由来の圧倒的なジャンプ力と、お馴染みのライダーパンチとライダーキックを駆使して戦う姿にはノスタルジーさえ覚えるが、ニチアサではお馴染みのド派手なエフェクトも無し。敵を倒すと爆発するどころか、シュワシュワと泡になって消えてしまうという初代仮面ライダーを意識した演出も、圧倒的に地味に見えてしまう原因だろう。
そもそも、PVからして地味だった。
映画のPVといえば、ド派手なアクションシーンや、登場人物たちが感情を爆発させるシーンがてんこ盛りの上、人気アーティストの主題歌をBGMにして感情を揺さぶるのが常となっているが、本作のPVは圧倒的に地味だった。人気アーティストの楽曲が用意されているわけでもなく、キャストも大半が明かされていなかった。実際には、かなりの人気俳優さんたちがキャスティングされていたわけだが、「それは観てのお楽しみ」と秘匿され続けた。そのため、映画館でたまたま本作のPVを観た、仮面ライダーにも庵野秀明にも興味のない人たちの目を惹くような効果は薄かったと言わざるを得ない。
キャラクターが描かれていない
「キャラクターの描写が薄く、感情移入できなかった」という意見も結構多い。
これには概ね同意する。ただし、そもそも『仮面ライダー』という作品自体、キャラクターをそれほど深掘りしている作品ではなかった。世界征服を目論む悪の秘密結社ショッカーによって無理やり改造人間にされてしまった主人公・本郷 猛が組織を裏切り、その身に宿してしまった超人的な能力を利用して世界平和のために戦うというだけだった。本人の意思など無視して「家業を継げ」と言われた息子が、そのやり方に反旗を翻し、親を断罪する、みたいな話だが、ショッカーと本郷の間には、親子のような深い縁があったわけでもないので、どこかふわっとしていて、共感するには難しい。『V3』以降の作品では、悪の秘密結社に家族や親友を殺されたから復讐する、といった共感できそうな“戦う理由”が付与されるが、はっきりと人間ドラマを重視するようになったのは『仮面ライダーBLACK』からだろう。それまでは、哀しい宿命を背負った正義の人、というアイコニックな存在でしかなかった。つまり、『仮面ライダー』を再構築する上では、キャラクターの描写が薄いというのは必然だったのではないか。共感できるほどの背景を持たせてしまったら、それはもはや『仮面ライダー』ではない、と言って良いのかもしれない(ただし、そうした新しい解釈を望んでいた、という人たちは多いのかもしれないが)。
そもそも、庵野さんの作品というのは、このアイコニックな登場人物が多い。各キャラクターに背景はあるものの、それは断片的にしか見えないことがほとんどであり、基本的には物語を駆動するための装置として存在しているように見える。それはキャラクター・ドリブンなんてものではなく、作品に込められた想いや哲学を伝えるための歯車とか回路といった方が相応しい。それは他のシンシリーズ全般に言えることで、振り返ってみると、作品として面白かったという感想はあっても、あのキャラクターに共感できた、といった感想はほとんどない。『エヴァンゲリオン』をTVシリーズから観ているファンなら「コイツ、何を言ってるんだ?」と思われるかもしれないが、何の知識もなく『シン・エヴァンゲリオン』を観たら、きっとそんな感じだと思う。
『シン・仮面ライダー』を観て、『エヴァンゲリオン』を思い出した人も多いようだ。私もそうだった。これが何を意味しているのかといえば、これはエヴァにしろライダーにしろ、庵野秀明という人の世界観を表現するための器だったということだ。エヴァやライダーがジャンプしてクルクルと空中で高速回転したり、キックしたまま敵を地面に叩きつける、といった表現は、庵野さんの考えるカッコ良さの象徴なのだろうし、人類補完計画のような人々の魂を一つにするという考え方には、庵野さんの中にある宗教観が垣間見える。
これを「ネタ切れ」だと思ってはいけない。自らの内にある世界観を表現するのがアーティストなのである。歌手が同じような楽曲ばかり作るのは、それが彼らの好きな世界だからだ。好きな音楽が多い人ほど引き出しが増えるというだけで、元々その人の世界観にないものは出てこない。マンガ家も同じだろう。同じような作品ばかりになってしまうのは、やはりその人の世界観ゆえである。
庵野秀明という人は、アーティストである。自身の中にある哲学や好きなものを表現するための道具として、創作活動を続けており、キャラクターを操っているのだ。共感してもらいたいのは、個々のキャラクターなどではなく、そこに流れる自らの思想ではないのか。
くれぐれも言っておくが、私個人は庵野信者ではない。TVシリーズの『エヴァンゲリオン』は面白いとは思ったけれど、熱狂したわけではなく、劇場版もアマプラで観た程度。『シン・ゴジラ』も『シン・エヴァンゲリオン』もアマプラだ。それでも、この人の作る作品には、他では感じられない何かがある。『シン・仮面ライダー』も例外ではない。
開始3分で虜になる
と、ここまではSNSで見かけた批判的な意見と、それに対する私なりの考察を示してきたが、続いては、私が本作を観て良かった点を書いてみたい。冒頭でも書いた通り、ネタバレはしないので安心していただきたい。
これも賛否両論あるけれど、本作のアクションシーンは決して悪くない。本作は“映倫PG12指定”とされており、「小学生には助言・指導が必要」らしい。いったい何を助言すれば良いのか全くわからない。この手の、クレーム対策のためにとりあえずしましたと言ったレーティングにはうんざりするが、残酷な描写があることは間違いない。小さな子には見せたくないと感じる親御さんもいらっしゃるだろうとは思う。ただし本作においては、その残酷さこそが作品にリアリティと深みを与えている。1980年代にブームを巻き起こしたスプラッタムービーのように、とりあえず血飛沫撒き散らしとけー!的な表現とは訳が違う。
仮面ライダーといえば、ライダーパンチやライダーキックといった必殺技が真っ先に浮かぶという人も多いだろう。その威力たるや凄まじく、仮面ライダー1号のライダーパンチは15.5t、ライダーキックは22tと言われる。昔から特撮では、技や武器の破壊力を示す際に「岩をも砕く」とか「厚さ◯㎝の鋼鉄をも貫く」といった例え話を用いていたが、その言葉通りの威力である。しかも、それ以上の力を持つ新たなライダーが次々に登場し続けている。例えば、平成最後の作品『仮面ライダージオウ』に登場したオーマフォームは、パンチ力129.9t、キック力は389.9tと比べものにならない。子どもと大人どころか、幼稚園児とメイウェザーほどの差がある(適当)。終わりのないパワーインフレだ。
しかし、それほどの威力を持つにも関わらず、これまでの作品の中で、その凄まじさをきちんと表現できたものがあったか?と問われれば、正直、首を傾げざるを得ない。もちろん、現在も仮面ライダーシリーズを放送しているニチアサ枠で、その凄まじさをリアルに表現するのが難しいことは理解できるが、変身前の主人公たちが敵ライダーにボコられるシーンを見るたびに萎えてしまう。生身で数十tものパンチをくらって生きていられるわけがないからだ。そこからは仮面ライダーの超人性がゴッソリ抜け落ちている。ただのケンカ自慢同士の戦いにしか見えない。それなら格闘技の試合でも観ている方が、よほど迫力を感じられる。
だが本作は、その超人性を見事に描いている。襲い来る戦闘員たちにパンチやキックが炸裂すると、マスクが潰れ、鮮血が噴き出す。ニチアサでは到底実現し得ないこういった表現が、仮面ライダーの持つ人智を超えた破壊力を鮮やかに描き出している。先述した、巨人や怪獣と比べると、人間サイズの怪人同士の戦いはどうしても地味になってしまうということの解決策としても悪くない。
こういう表現に対する規制は年々厳しくなっている。特に子どもたちに対しては、まるで世界の美しい部分だけを切り取って見せなければならない、といった雰囲気さえある。だが、そもそもこの世界は醜いことばかりだ。終わらない暴力の連鎖。その日の食事にさえ困る人たちがいることを知りながら、SNSで華やかな生活を見せつける一部の富裕層。そういった醜悪な現実から目を逸らさせることが真の教育と呼べるのだろうか。欲に駆られた人々によって汚らしく塗り固められた世界に、たった一人でも抗うのがヒーローだろう。こんなもの子どもに見せられるかって人は、朝から晩まで、愛と勇気だけが友達なあの人を見せておけば良いだろう。
ここまで、上映開始からたった3分。この時点で私はすっかり本作の虜になっていた。これまで飽きるほど観てきた仮面ライダーという作品に対するイメージを、たった3分の映像表現であっさり塗り替えてくれたのだ。今、我々が本当に観たい仮面ライダーと言って良い。50周年記念として『シン・仮面ライダー』が発表された時に勝手に予想した通りになったことも、私個人としては嬉しかった。
ラストバトルが、みっともない泥試合になるところもまた見ものだ。死闘という表現がまさにしっくり来る。
ただし、アクションの全てが良かったわけではない。1号ライダーと2号ライダーによる空中戦は、「ドラゴンボールか?」みたいな感じで少々眠たかったが、一番気になったのは、ショッカーライダー(偽ライダー)たちとの戦いの場面だ。暗い場面で黒い体色のショッカーライダーたちとごちゃごちゃ戦っているシーンを、わざと手ブレさせたような映像で描いたのは、以前、庵野さんが「子どもの頃に観た仮面ライダーで印象的だったのは、夜のビルの屋上でライダーと戦闘員が戦うシーン。真っ暗な中で黒っぽい人たちが戦っているのは、何をしているのかよくわからなかったけどカッコ良かった」とインタビューで語っていたが、まさにそれの再現だろう。「ノスタルジーは捨てたくない」とも言っていた、その言葉通りに、50年前の庵野少年がカッコ良いと感じたシーンを再現したつもりなのだろうが、少なくとも今の私にはピンとこなかった。人によっては画面酔いするのではないか? なんて余計な心配をしてしまうレベルだった。
さらに、“仮面”にこだわったところもまた本作の特徴である。主人公・本郷 猛だけでなく、2号ライダー・一文字隼人もヘルメットのような仮面を被る。敵もまた然りで、体組織そのものが変化するのではなく、仮面を被ることで変身が完了するのだ(コウモリオーグは除く)。仮面を被った本郷の首元から襟足が覗いているのは、その被り物感を強調しているが、これは『仮面ライダー』初期の頃へのオマージュでもある。あの頃、仮面からはみ出していた襟足が、仮面を被っているという表現のためだったのか、それとも造形の未熟さ(低予算のため?)だったのかは知らないが、そこに着目するというだけで、ファンはニヤリとしてしまう。本郷 猛を演じた池松壮亮さんがロン毛なのも、それを表現するためだったのだろう。
造形の良さもまた特筆すべき点である。リブートされた1号や変身ベルト(タイフーン)、サイクロンのカッコ良さは凄まじいが、敵怪人も負けず劣らずカッコ良い。初代『仮面ライダー』に登場した怪人たちは、いずれも生物感が強かったが、本作ではクモやハチなど、生物と機械を融合したマスクを被る怪人が複数登場。いずれもデザインや質感、さらにLEDでライン状に光る眼など、非常にカッコ良く、ザコ感はまるでない。
ラストに至る流れも良かった。無理やり畳んだ感はなく、最後にファンならニヤリとさせられるシーンも待っている。ラストだけでいえば、間違いなく『シン・ウルトラマン』よりこっちだろう。
俳優陣・スタッフにもエールを
2023年3月31日にNHK BSプレミアムで『ドキュメント「シン・仮面ライダー」〜ヒーローアクション挑戦の舞台裏〜』という番組が放送された。『シン・仮面ライダー』の撮影現場に2年間密着取材したドキュメンタリーだ。『シン・エヴァンゲリオン』の時にも同様のドキュメンタリーが放送されており、その際にも現場のピリついた雰囲気は伝わってきたが、今回はそれどころではない険悪な空気が話題となった。
その際の庵野さんのやり方などを見て「パワハラでは?」などという批判も多いようだが、私たちは切り抜かれて放送された部分しか知らないわけで、その一部だけを見て是非を問うべきではないと思っているので、ここでその話には触れないが、参加した俳優さんたちとスタッフさんたちが大変な苦労をされたことだけは理解できた。
『シン・仮面ライダー』という作品を語る時、どうしても庵野英明という名前ばかりが前面に出てしまうのだが、作品を実際に鑑賞してみれば、主役、脇役を問わず、ショッカーの戦闘員一人一人に至るまで、非常にクオリティの高い演技を見せてくれているのがわかる。
みんな大好き浜辺美波さんのツンデレな演技は言うまでもなく(泣きたくなった時に「胸貸して」と言うのは、ちょっと時代錯誤すぎる感じはあったけれど)、これまでほとんど知らなかった池松壮亮さんや柄本 佑さんらの熱演には胸を打たれた。森山未來さんの安定感は抜群だったし、まさかの長澤まさみさんの登場には素直に驚いたし、ハチオーグを演じた西野七瀬さんもとても良かった。先述した通り、本作は出演俳優さんのネームバリューをほとんど宣伝に使っていないという特殊な作品である。主演俳優を安易に売れっ子にしなかったことも作品の雰囲気を第一に考えたからだろう。それでも、できあがった作品を観れば、おそらく誰もが出演俳優さんたちの虜になるはずだ。作品そのものに対する賛否は別として、俳優さんたちの鬼気迫る演技は間違いなく一級品である。
しかし、その裏に大変な苦労があったことは間違いない。劇場挨拶の際に池松さんが語った「こんなに追撮(追加撮影のこと)をする監督は他にない」という言葉からも、庵野さんの並々ならぬこだわりに、俳優さんもスタッフさんも翻弄され続けたことがわかる。撮影には、iPhoneなども含めて16〜17台ものカメラを使っていたと言われており、それらを管理するだけでも大変だったろう。大変だったのは、番組で取沙汰された田渕アクション監督だけではない。全ての俳優さん、全てのスタッフさんが等しく大変だったのだ。
その苦労が報われたかどうかは私などにはわからないけれど、それでもこうして完成した作品は、まさに関係者一同の血と汗と涙の結晶である。
怖いもの見たさでも構わない。もしも迷っているなら、是非一度観て欲しい。その結果、面白かろうがつまらなかろうが、心に引っかかる何かがある作品であることは断言できる。視聴後、何の印象も残らない作品もある中で、これだけ癖の強い作品は珍しい。私もあと2回は観に行きたい。
なお、他の記事でも書かれているように、TVシリーズ『仮面ライダー』や石ノ森章太郎先生のマンガ版などを知っていれば、作品のあちこちに散りばめられたオマージュにニヤリとできることは間違いないので、ご興味があれば是非手に取っていただきたい。
さらに、本作に登場する緑川イチローの背景を知りたい方は、マンガもあるのでそちらもチェックしていただきたい。
それでは、最後までおつきあいいただきありがとうございました。
\ 僕と握手! /